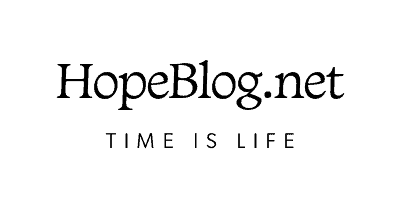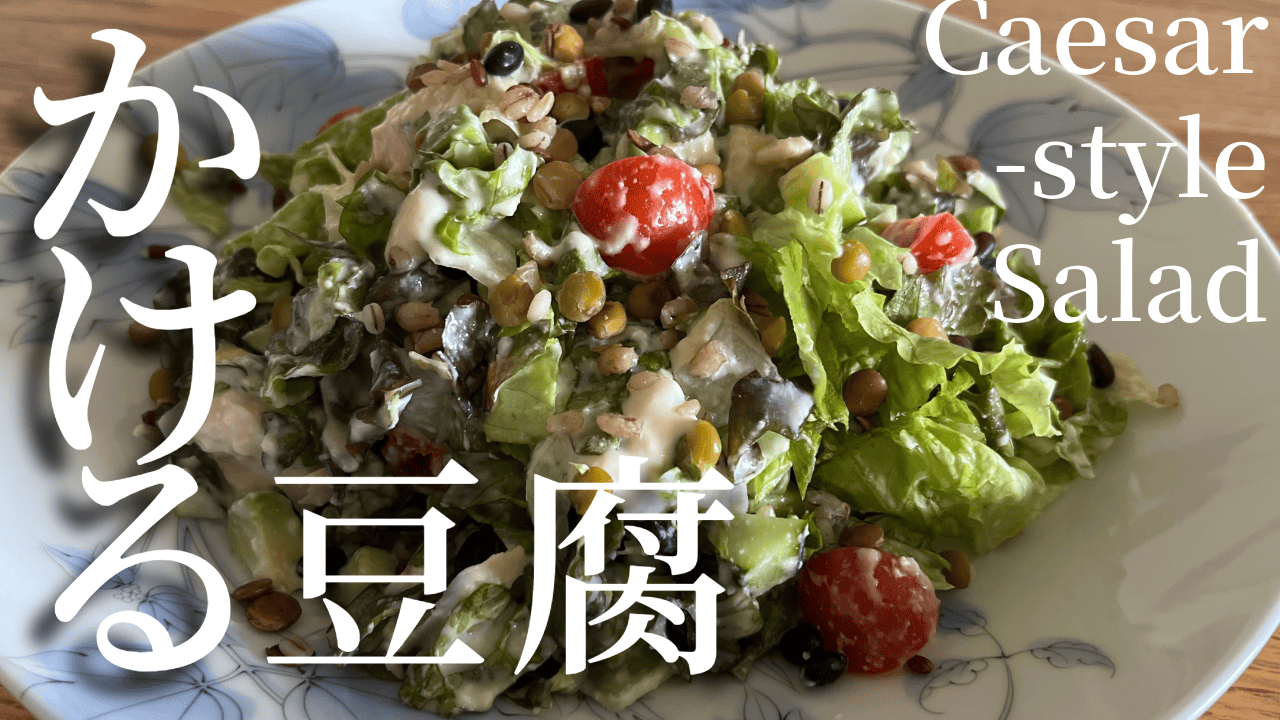お粥を食べるメリット
胃に優しく消化吸収が良い
お粥が昔から病中病後の回復食に作られてきたのは消化吸収が速やかだからです。
お米をたっぷりの水分で炊く事によりαでんぷん化(のり状に変化)し、胃での滞留時間が短く胃腸への負担が軽減されます。
体調を崩したときや手術のあと、また離乳食や介護食、ファスティング明けなど、さまざまな場面で活躍します。
水分量が多い事により咀嚼回数が少なくても食べやすく飲み込みやすいのが特徴です。朝の脱水気味な体には水分補給と温活が同時にでき、内臓温度を上げる事で代謝も上がります。
ダイエット中のカロリーコントロールに
ごはん茶碗1杯量を食べ比べるとおかゆのカロリーはごはんの半分程度になります。同じく糖質量も抑えられるのでインスリンの過剰分泌を防ぎ脂肪の蓄積を予防する効果も期待できます。
味付けやアレンジ次第で栄養の調整がしやすい
和洋中に加えエスニック、薬膳やスイーツ風まで幅広くアレンジができ、体調やシチュエーション、好みに合わせられます。付け合わせを増やすと見た目も栄養価もぐっと上がります。
余ったものを活用しフードロス削減
お米から炊く基本的なお粥の他にも残ったご飯や冷蔵庫の余り物など残った食材でリメイクがしやすいのでフードロスにつながります。また干物や乾物、肉や魚などとも相性がいいです。
今回は、基本のお粥の他に私が日常的に作っている3種のお粥を後ほどご紹介します。どれも簡単に作れて、それぞれにちょっとした“工夫”や“整え効果”があるレシピです。食事で身体を整えたい方や朝食に迷っている方はぜひ参考にしてみてください。
お粥の種類と段階的な柔らかさ
基本の全粥

<材料>2人分
- 米1/2合
- 水600cc
- 塩ふたつまみ程度
○基本のお粥はお米から炊き上げます。(我が家は土鍋で作りますが普通の鍋でも勿論大丈夫です。)
○洗ったお米と水を鍋に入れ、かき混ぜながら沸騰させます。
○沸騰したら弱火に落とし蓋をして30分から40分炊き上げます。
(蓋は少しずらして吹きこぼれない様にしておきます。)
○仕上げに塩をふたつまみほど入れて完成。
○梅干しやお漬物などお好みのものを添えます。
米から炊くお粥が一番美味しいですが、私は余ったご飯や冷凍ご飯で簡単にお粥にする事も多いです。
土鍋でそのまま食卓に出すと優しい雰囲気に和みます。小ぶりでも深さがあるタイプが吹きこぼれにくくおすすめです。
詳しくはAmazonで見てみる🔽
【Amazon】萬古焼 土鍋(中サイズ)① 鶏ささみ・生姜・梅干し入りの「卵とじ和風粥」

<材料>2人分
- ご飯1膳分(約150g)
- 鶏ささみの茹で汁(無い時は水)500cc
- 鶏ささみ1本分
- 生姜ひとかけ(千切りかみじん切りまたはすりおろす)
- 梅干し1個
- 卵1個
- 好みで塩や塩麹適量
- 小ネギや胡麻
○鶏ささみは茹でて茹で汁をとっておく
(レンチンささみを使う時は鶏がらスープの素などで味を整える)
○茹でたささみをほぐして、潰した梅を和えておく
○鍋にご飯と茹で汁、その他の材料を全て入れ火にかける
○混ぜながら沸騰するまでは中火で、沸騰したら最弱火にして蓋をする
(吹きこぼれ防止に割り箸一本分くらいずらして開けておく)
○15分ほど弱火のまま炊き上げて好みの柔らかさになったら完成
淡白ながら旨味のある鶏ささみと、体を温める生姜を使った定番のお粥。ポイントは仕上げに入れる溶き卵と、梅干しの酸味。これが味に奥行きを与えてくれます。
【健康ポイント】
・鶏ささみは高タンパク低脂質。カロリーを抑えながらもしっかりタンパク質を摂りたい時にぴったり。
・生姜にはショウガオールという成分が含まれ、身体を内側から温め、冷え性改善や免疫力UPに効果的。
・梅干しはクエン酸が豊富で、疲労回復に役立つ上、殺菌作用も。食中毒予防にも昔から使われてきた伝統的な発酵食品です。
・完全栄養食と言われる卵を最後に加えることで、さらに満足度もUP。
味のバランスも絶妙で、ほっこりとした気持ちになれる一杯です。
② 干しエビ・干し貝柱・油揚げ入りの「中華風月見粥」

ちょっと贅沢に感じられるのが、乾物の旨味を生かした中華粥。干しエビや水戻しした貝柱の出汁と一緒にコトコト煮ることで、加えた油揚げにもうま味成分がじんわり染み込みます。仕上げに片栗粉でとろみをつけてから卵黄を落とす「月見仕上げ」にすることで崩しながらクリーミーな食感を楽しめます。
【健康ポイント】
・干しエビ・貝柱はカルシウム、マグネシウム、亜鉛などのミネラルが豊富。乾物にすることで栄養素がギュッと濃縮されています。
・油揚げを加えると植物性たんぱくと油分がプラスされ、コクと栄養バランスがアップ。
・食欲のないときでも片栗粉のとろみで喉越しが良くなります。
中華だしの風味と、乾物の旨味が重なるこの一杯は、まるで小さなご褒美のようなお粥。体にじんわり沁みわたる一品です。
③ ほうじ茶・さつまいも・10種の豆のお茶粥
最後はめぐる・潤う・整う、レシピ。さつまいもと豆をたっぷり入れて香ばしいほうじ茶を使ったお粥。
タンパク質と食物繊維たっぷりに腹持ちも良い一皿に仕上げます。具材を煮るだけで作れるので、炊いたごはんのリメイクにもぴったり。
【健康ポイント】
・ほうじ茶にはカフェインが少なく、リラックス作用のあるテアニンも含まれます。香ばしい香りは気分を落ち着けてくれます。
・さつまいもは食物繊維とビタミンCが豊富。腸の動きを促してくれるので、便秘気味の方にもおすすめ。
・10種の豆にはそれぞれにポリフェノール、たんぱく質、ミネラルが含まれており、まさに“食べる薬膳”。色も食感も楽しいお粥になります。ほんのり自然の甘みを感じるこのお粥は、心までやさしくなれる味わいです。
【まとめ】やさしさを食べる食習慣
お粥と聞くと「病気の時に食べるもの」というイメージがあるかもしれません。
しかし好きな具材をごはんと共に炊くだけで心身が整うおかゆがアレンジ無限に作れ、元気な時でもさらに身体作りができるのです。
育ち盛りやスポーツをしてる時など、特にカロリーを摂りたい場合には切り餅を加えたり、濃いめの味付けにした肉や魚を後からのせるのもおすすめです。
余談ですが、麹水について書いている記事があります。(余す事なく活用する麹水レシピ)米麹を水に浸すだけで飲めるほんのり甘い麹水です。麹水を飲んだ後の米麹もお粥に再利用できるのでこちらも良かったら合わせてお試しください。
今回ご紹介した4種のお粥は、どれも身体を整える素材で作る“食べる養生”。忙しい朝にも無理なく食べられて、胃腸にやさしく、心まで整えてくれる味です。
季節の変わり目や、少し疲れたなという時。そんな時にこそ「何を食べるか」が、体調や気分を左右することを、私自身の経験からも感じています。
またお米が高くて手に入りにくり昨今、健康のみならずお米の消費が節約できるのも嬉しい効果かもしれません。